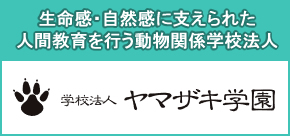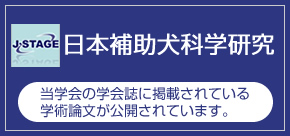一般社団法人
日本身体障害者補助犬学会Japanese Society of Service Dog Research
賃貸住宅/分譲マンション編パンフレット(テキスト版)
- 現在位置
- ホーム > 賃貸住宅/分譲マンション編パンフレット(テキスト版)
もっと!どこでも補助犬同伴ミニブック~賃貸住宅・分譲マンション~
補助犬とユーザーはどこでも一緒
- 補助犬とは補助犬は盲導犬・介助犬・聴導犬の総称です。
- 盲導犬 目の不自由な人の安全な歩行をサポート
【イラスト】盲導犬ユーザーと盲導犬
胴に白、または、黄色のハーネス着用
- 介助犬 体が不自由な人の日常生活をサポート
【イラスト】介助犬ユーザーと介助犬
介助犬の表示の入った胴着着用
- 聴導犬 耳が不自由な人の必要な生活音をサポート
【イラスト】聴導犬ユーザーと聴導犬
聴導犬の表示の入った胴着着用
- 補助犬同伴の受け入れ義務
補助犬を同伴しての利用を拒否してはいけません。身体障害者補助犬法・障害者差別解消法で定められています。
- 国や自治体が管理する施設
- 電車、バスなどの公共交通機関
- ホテルやレストラン、デパートなど不特定多数が利用する民間施設
- なくそう! 補助犬への先入観や誤解
実際の受け入れで、他の利用者からの苦情はほとんどありません。苦情の内容は補助犬の問題ではなく従業員の理解不足による対応の不備が多くなっています。
Q . 他の利用者から苦情をうけたことがありますか?
【円グラフ】ショッピングセンター(苦情を受けたことが)ない:83% ホテル(苦情を受けたことが)ない:77% 飲食店(苦情を受けたことが)ない:93% (出典:身体障害者補助犬の普及・啓発のあり方に関する調査研究報告書 令和2年3月)
障害のある人の社会参加を支える補助犬
- 身体障害者補助犬法が定める3つの義務
身体障害者補助犬法には3つの柱があり、訓練事業者には質の高い補助犬の育成と指導、補助犬法に基づいて認定を受けたユーザーには補助犬の健康・衛生管理と周囲に迷惑をかけない行動管理、社会には補助犬同伴の受け入れを義務付けています。
質の高い補助犬の育成
【イラスト】トレーニングしている犬とトレーナー 訓練事業者 ↔ 健康・衛生・行動管理
【イラスト】介助犬ユーザーと介助犬 補助犬とユーザー ↔ 同伴の受け入れ
【イラスト】補助犬ユーザーの周囲を社会の人が取り巻いている 社会
- 障害のある人もない人もお互いに尊重し合いながら共生できる社会とは
- 補助犬を同伴する障害のある人が安心して行動できる社会
- 補助犬の存在を安心して受け入れられる社会
- 補助犬にまつわる法律の理解とコンプライアンスの重要性
- 身体障害者補助犬法とは
公共交通機関、お店や病院など不特定多数の人が利用する施設などで、補助犬同伴の受け入れをスムーズに行い、身体に障害のある人の自立と社会参加を促進することを目的として定められた法律です。
!一般の人が利用できる施設等への補助犬同伴の受け入れを求めています。
- 障害者差別解消法とは
障害のある人もない人も、お互いに、その人らしさを認め合いながら、ともに生きる社会を作ることを目的とした法律。国・地方公共団体・事業者に対して、「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮」の提供を求めています。
!補助犬の同伴を理由に受け入れを拒否することは、不当な差別にあたります。
認定をクリアした補助犬とユーザー
- 補助犬の安全と安心を担保するシステム
ユーザーと補助犬のペアで能力が認められて、初めて社会参加が可能に
- 補助犬:社会で他人に迷惑をかけず、適切な行動をとれる
- 補助犬ユーザー:補助犬の健康・衛生・行動面を管理できる
【イラスト】携帯をユーザーに渡す介助犬
国や自治体による社会の受け入れ義務の啓発
【図】国・自治体→(社会の受け入れ義務(受け入れ努力義務))→公共交通機関・レストラン・民間施設・企業等
- 補助犬ユーザーの義務
補助犬ユーザーには補助犬の健康・衛生管理および行動管理が義務付けられています。
- 健康管理:予防接種、定期康診断など
【イラスト】獣医師に診察されている補助犬・衛生管理:ブラッシング、シャンプー、抜け毛予防など
【イラスト】補助犬のブラッシングをするユーザー・行動管理:適切な場所で指示による排泄、咬まない、吠えないなど
【イラスト】ペットシーツの上で排泄する補助犬
補助犬ユーザーと補助犬への対応
- 認定基準を満たしたユーザーと補助犬のしるし
補助犬の表示と認定証の携帯はユーザーの義務となっています。
【写真】ハーネスをつけた盲導犬、介助犬とユーザー、介助犬の表示、身体障害者補助犬認定証、盲導犬使用者証、身体障害者補助犬健康管理手帳
!ハーネスや表示の入った胴着が目印 身体障害者補助犬法では、補助犬の表示の義務と、補助犬ユーザーには認定証(盲導犬ユーザーは使用者証)の携帯を義務付けています。補助犬かどうかの確認が必要な場合は、「認定証を確認させていただけますか?」と声をかけましょう。
- 補助犬と補助犬ユーザーへのサポート
- 補助犬への接し方
補助犬が作業に集中できるよう(落ち着いて待機できるよう)、食べ物を与えたりむやみに触ったりするなど、気をひく行為は避けましょう。
- 補助犬ユーザーへの対応
お困りの様子が見られたらユーザー本人に「何かお手伝いしましょうか」「どのようにお手伝いすればよろしいですか」などの声かけや筆談でコミュニケーションをとりましょう。
不慣れな場所への誘導【イラスト】盲導犬ユーザーに肘を貸して誘導する様子。
乗り越えられない段差の介助【イラスト】介助犬ユーザーの車いすを押して段差を乗り越える様子
館内放送や電車内のアナウンスの伝達【イラスト】筆談をしながら、口をはっきり開けて聴導犬ユーザーに話しかけている様子。
- 賃貸住宅・分譲マンションにおける補助犬の同伴
補助犬は補助犬ユーザーがきちんと行動・衛生管理をしていますので、部屋を汚したり、傷つけたりすることは基本的にはありません。補助犬のことを知って前向きな受け入れを賃貸住宅ではペットの飼育を禁止している物件が多く、家主との個別の交渉を必要とするのが現状です。しかし、家主への補助犬の正しい情報提供も含めて、物件仲介を行うことは、家主にとっては空室のリスク減、補助犬ユーザーにとっては住居の確保となりwin-win の関係構築となりえます。
【イラスト】介助犬ユーザーが物件の案内を受けている。住人の親子もにこやかに挨拶している様子。
Qペット不可物件、補助犬同伴の申し込みがあったら?
まず家主に、補助犬は「ペット」ではないこと、補助犬法により受け入れの努力義務があることを説明しましょう。他の入居者にも、ユーザーと一緒にいるのは「ペット」ではなく「補助犬」であることを説明しておくとよいでしょう。
【イラスト】ベッドの下の敷物の上で休む補助犬
Q物件には、特別な改修工事や設備が必要?
補助犬を飼育するために、特別な改修の必要はありません。一方で、ユーザーの障害に適した設備を求める場合があります。例えば、車椅子を使用している場合、「段差がない」または「スロープがある」などを希望することもあるでしょう。しかし、ニーズは人それぞれです。どのようなニーズがあるか、本人に聞いてみるとよいでしょう。
【イラスト】盲導犬、介助犬、聴導犬
Q補助犬ユーザーに限って付帯特約を付けてもよい?
補助犬を理由に、他の入居者とは異なる契約(特約)内容を結ぶのは適切ではありません。家主が補助犬の受け入れに不安を持っている場合は、ユーザーにその不安を伝え、特約の設定について理解を得ることも検討してみましょう。【イラスト】机に向かって仕事をするユーザー、補助犬は足元で待機している
Q入居後、他の入居者とトラブルにならないようにするには?
他の入居者への事前説明と確認がポイントです。補助犬は住宅の中で吠えたり、暴れたりしないこと、衛生管理が徹底されていることなど、補助犬の正しい情報を提供します。その上で、何か不安がないかを事前に確認します。【イラスト】粘着テープで下に落ちた毛を清掃する補助犬ユーザー
- 生活基盤である住宅、すべての人が安心して暮らすために
ユーザーの声:「補助犬がいると、きっと家主に断られるだろう」と判断され、仲介に至らないことがあると残念です。家主へ補助犬の正しい情報を提供し、予断を持たず、親身になって対応してくれるとうれしいです。
- 他の入居者への対応 ─トラブルを防ぐために
補助犬の同伴に対する方針の明示、日ごろから理解を求める
- 補助犬同伴の受け入れは障害のある人の生活を守るための権利保障であること
- 補助犬は適切な管理をなされた犬であり、安心して受け入れられること
譲り合いの精神を持つ
補助犬の同伴を受け入れる際に不安や気になることがあったら、ユーザーにそれを説明し、お互いが納得のいく方法を見いだしましょう。
- 補助犬ユーザー受け入れガイドブック 宿泊施設編
より詳しい情報(対応・受入れ事例)はガイドブックをご覧ください。
QRコード
- 受け入れを円滑にするためのチェックリスト
【補助犬と補助犬ユーザーに関する知識の習得】
□コンプライアンス:補助犬法と障害者差別解消法
□補助犬と生活する障害のある人
□補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)の役割
□補助犬の安全性(衛生、健康、行動)
□補助犬とペットの違い
□障害に合わせた接遇
【スタッフ教育(不動産会社・管理会社)】
□補助犬ユーザーと補助犬に関する知識の習得
□補助犬ユーザーの接遇に関する教育
□家主への啓発・補助犬ユーザーと補助犬に関する情報案内
□ペット不可物件における説明
□他の入居者への啓発・対応
【施設内バリアフリーと設備】
□住居のバリア(段差や障害物など)の把握
□住居スペース(通路の幅など)や設備の把握
【入居希望時の要望確認】
□補助犬ユーザー自身が生活上特別に必要な設備の有無
□補助犬と生活する上で特別に必要な設備の有無など
【契約時】
□原状回復義務についての確認(補助犬が原因によるものも適用されること)
□補助犬訓練事業者とその連絡先の把握
※「補助犬ユーザー受け入れガイドブック・賃貸住宅編チェックリスト」を抜粋・加工。詳細・分譲マンションについては「同ガイドブック 賃貸住宅・分譲マンション編」をご確認ください。
- ほじょ犬マーク
身体障害者補助犬法の啓発のためのマークです。身体障害者補助犬とは、盲導犬、介助犬、聴導犬のことを言います。「身体障害者補助犬法」において、公共の施設や交通機関はもちろん、デパートやスーパー、ホテル、レストランなどの民間施設は、身体障害のある人が身体障害者補助犬を同伴するのを受け入れる義務があります。補助犬同伴受け入れに向けた啓発のためのステッカーやハンドブックは、下記、補助犬担当窓口で配布しています。
- 補助犬に関する詳しい情報
補助犬に関する関係法令やガイドブックなどのより詳しい情報をお知りになりたい方は、厚生労働省ウェブサイト内「身体障害者補助犬」のページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/hojoken/index.html QRコード
- 補助犬に関する相談・お問合せ先
補助犬同伴受け入れでトラブルが起こった場合の報告・相談窓口は、各都道府県・政令指定都市・中核市の障害福祉担当課へご連絡ください。
都道府県身体障害者補助犬法担当窓口一覧
https://www.mhlw.go.jp/content/000465967.pdf
QRコード
事業者用補助犬ユーザーの受け入れ方(日本補助犬情報センター動画)
QRコード
先頭へ